東京メトロに乗っていて、こんな経験はありませんか?
駅に到着して「〇〇駅、〇〇駅です」と放送が流れ、発車メロディー・扉が閉まる注意喚起の放送が入って、いよいよドアが閉まり始める…そのときです。
「〇〇線、△△線、□□線はお乗り換えです」という乗り換え案内が、ドアが閉まった直後に流れることがあります。
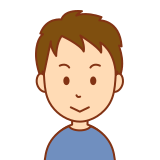
え、それ、もっと早く言ってよ!
と心の中でツッコんだ方も多いのではないでしょうか。特に、乗り換えをうっかり忘れてしまったときにその案内を聞くと、なおさらやるせない気持ちになりますよね。
扉を閉めた後に乗り換え案内をするのは不自然に感じます。
なぜこうなったのか東京メトロに質問しました。
具体的な発車時の流れ

東京メトロではドアを閉めて発車する際に
「ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。(大抵ここで扉が閉まり始める) Please stand clear of the closing doors.」
の注意喚起放送のあとに「〇〇線、●●線,…,□□線はお乗り換えです」と乗り換え路線の放送が続きます。
東京メトロに聞いてみた

なぜ乗り換え案内の放送は扉が閉まったあとに流れるのでしょうか?
この疑問について、私は実際に東京メトロお客様センターに問い合わせをしてみました。
結論から言うと、発車直前の乗り換え案内は「乗り過ごした人」や「乗換を忘れた人」に向けたものではないのです。
東京メトロからいただいた回答のは以下のようなものでした(一部抜粋)。
従前は駅名の放送後に乗換案内放送を行っておりましたが、発車メロディが鳴動すると乗換案内放送が途切れてしまっておりました。
自動放送自体は、限られた時間に必要なご案内を行っているため、乗車するお客様への注意喚起等が終了したタイミングで降車されたお客様向けに乗換案内の放送を行っております。また駅到着時には、車内放送で「到着駅名」と「乗換案内」をアナウンスしており、合わせて車内LCDにおいても乗換案内を表示させていただいておりますため、お申し出のような順序で放送となっております。
ポイント
✅以前は駅名の放送後に乗換案内だった
昔は駅名の放送後にすぐ乗換案内を流していたが、発車メロディが流れると、放送が途中で途切れることが多かった。
それを避けるために、注意喚起のあと(ドアが閉まり始めたあと)に放送順序を変更。
✅乗換案内の主な対象は「ホームにいる人」
発車直後の乗換案内はドアの外=ホーム上の乗客に向けたもの。
降車した人がホームで案内を聞けるようにすることで、他路線へのスムーズな乗換を促している。
✅到着時にも案内している
駅に着いたときの車内放送とLCD(車内モニター)で、すでに乗換情報は案内済み。
まとめ:少し不思議な放送にも意味がある
たしかに、発車間際の乗換案内は「もっと早く言ってほしい」と感じるタイミングですが、それはホーム上の人に聞こえるタイミングを考えた結果でもあるようです。
放送では限られた時間の中で、到着駅名・注意喚起・乗り換え案内すべてを完璧に伝えるのは難しいという現実があります。
つまり、あの「今!?」というタイミングには、複数の事情と工夫が詰まっていたんですね。
疑問に感じていた方も、少し納得していただけたのではないでしょうか。鉄道のアナウンスひとつ取っても、そこには思いがけない理由があるのですね。
こちらの記事もぜひ参考にしてください^^
x(twitter)でも大学生活などの役立つ情報を発信しています。
ぜひフォローしてください🙇♀️
アカウントはこちら
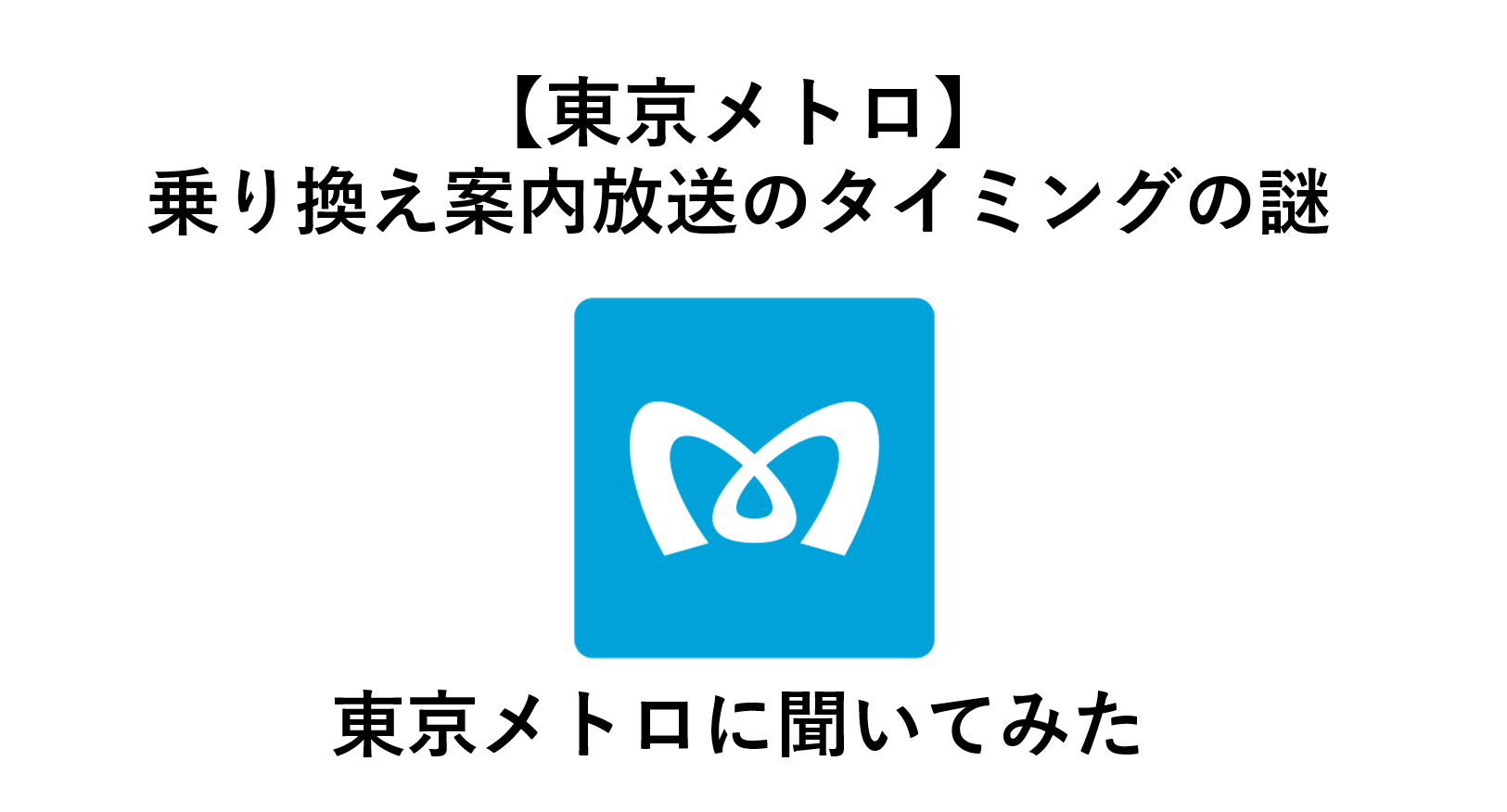
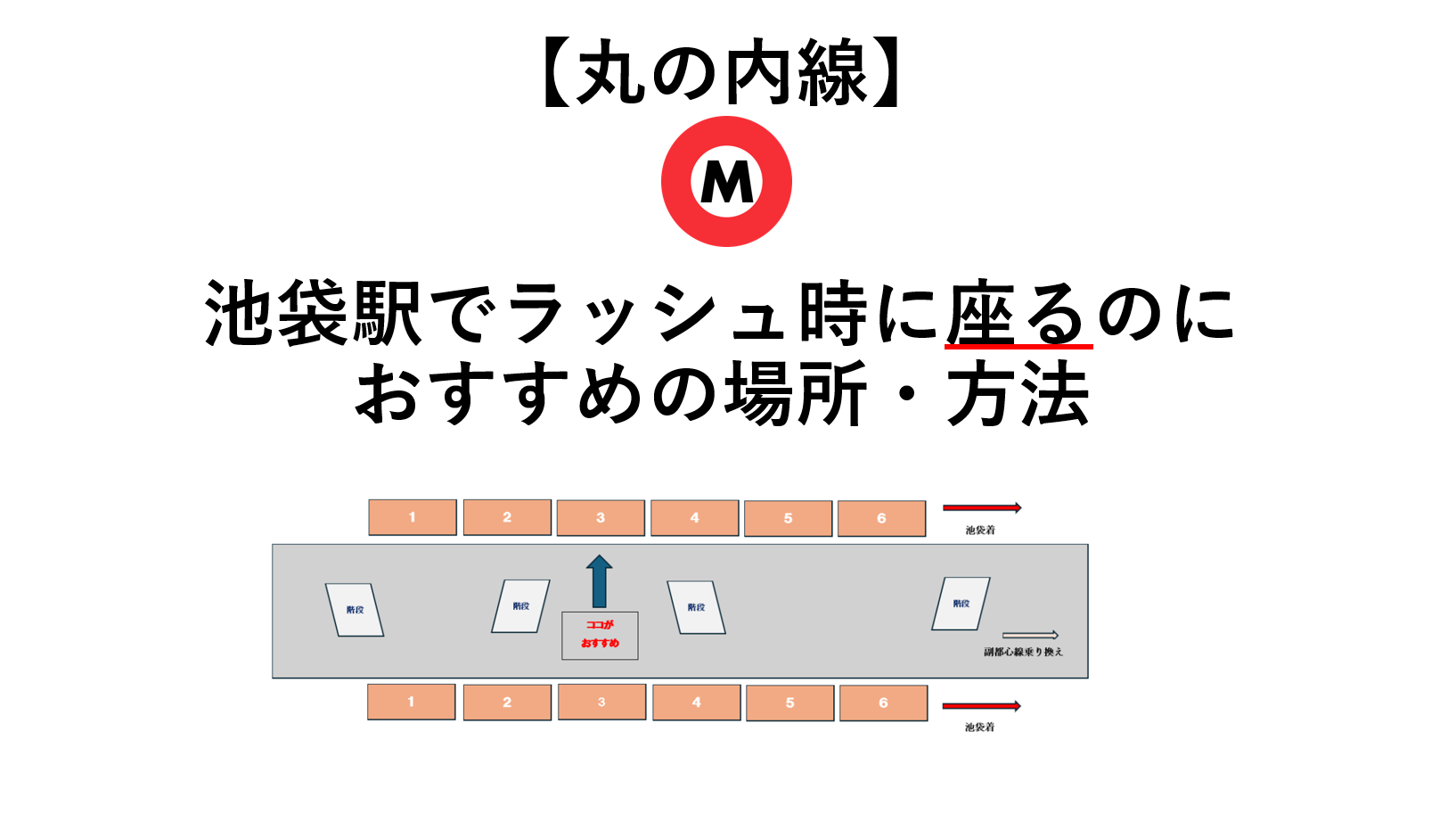
コメント